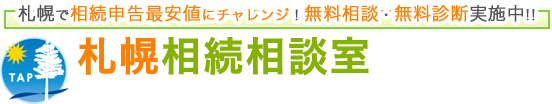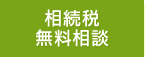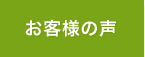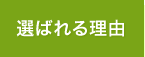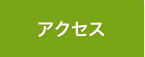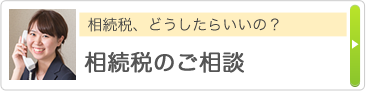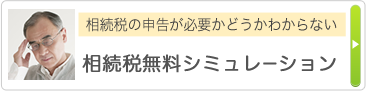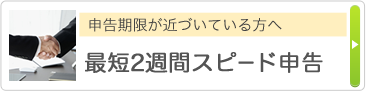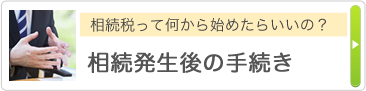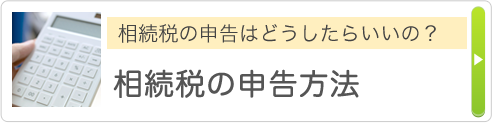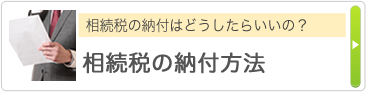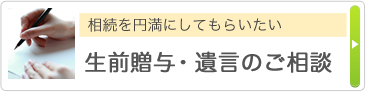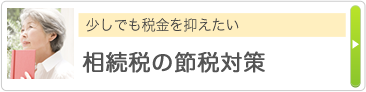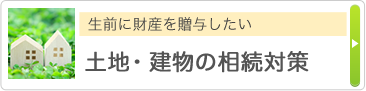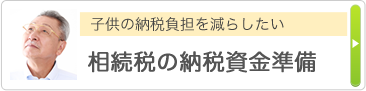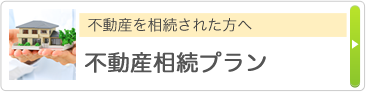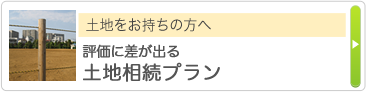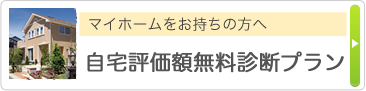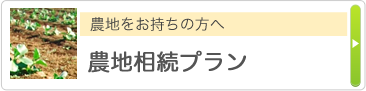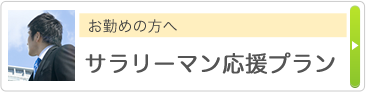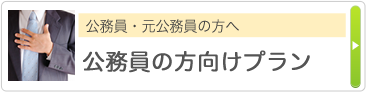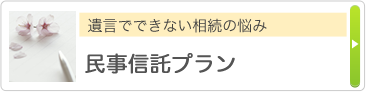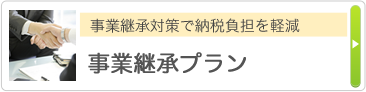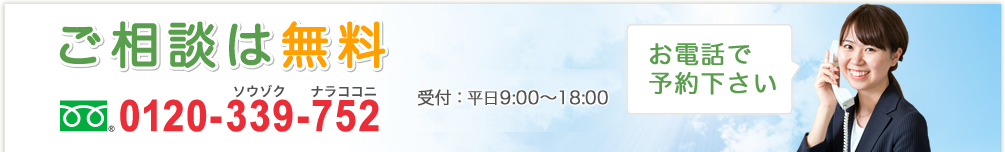新着情報
相続については沢山やらなければならないことがあり、とても大変でしたので、しんらいできるプロの方にお任せして少しでも負担を軽くするといいと思います
・ご相談内容
相続税申告
・満足度
とても満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、ご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
平日仕事をしているため、手続きをどのように進めていけばいいのか不安でした。
2.札幌相続相談室にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
また相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きくだ
続きを読む >>
期間がさしせまっているなか、快く受け付けて下さり、助かりました。
・ご相談内容
相続税申告
・満足度
満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、ご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
必要書類や計算書など経験のないことばかりで、面倒さが先に立って作業が全くはかどらず困っていました。
2.札幌相続相談室にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
また相談を受けていただ
続きを読む >>
夫の籍に入っていない事実婚の妻の相続はどうなりますか
「内縁の妻(夫)」には、内縁相手からの相続権がありません。
内縁によってできた子どもにも、そのままでは父親からの相続権がなく、自分の子どもだという父親の「認知」が必要です。(一方、母親からの相続権は「産んだ」事実によって当然に認められます。)
(上記は更新日時点での内容となります。)
続きを読む >>
親より先に子どもが亡くなっているときの相続はどうなりますか
その子どもの子どもが「代襲相続」によって相続できます。
亡くなった子どもが相続するはずだった相続分が、そのお子さんたちに受け継がれます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
続きを読む >>
亡くなった人の兄弟姉妹が相続出来るのはどういう場合ですか
兄弟姉妹が相続出来るのは、亡くなった人に子どもも親もいない場合です。
配偶者がいて、子供も親もいない場合は、
配偶者(妻または夫)=遺産の4分の3
兄弟姉妹=遺産の4分の1
となります。
仮に亡くなった人に妻(夫)がおらず、親と兄弟姉妹がいる時は相続人になるのは親だけで
兄弟姉妹には相続権が生じません。順位の低い者はいっさい相続出来ないのが法定相続
のルールだからです。
&
続きを読む >>
亡くなった人の親が相続できるのはどういう場合ですか
親が相続出来るのは亡くなった人に子どもがいない場合です。
子どもがいても相続を放棄するなどの事情があると、相続人ではないこととなり、親が相続することが出来ます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
続きを読む >>
遺言のない相続では妻(夫)と子はどのような割合で受け取れますか
法定相続ルールでは
配偶者(妻または夫)=遺産の2分の1
子ども=遺産の2分の1
です。
①子どもがいるとき
→奥さんと子どもだけが相続人になれます(親や兄弟は×)
②子どもがいないとき⇒→奥さんと親、兄弟姉妹がいる
→奥さんと親だけが相続人になれます(兄弟姉妹は×)
③子どもがいないとき⇒奥さんと兄弟姉妹がいる(親はいない)
→奥さんと兄弟姉妹が
続きを読む >>
遺言がない場合には誰が相続できるのでしょうか。
A.民法の決めた相続順位にしたがって相続人が決まります。
法定相続では、子供が最優先の相続人となり、他に相続出来るのは配偶者(妻・夫)となります。
親が相続出来るのは亡くなった人に子供がいないとき、また兄弟姉妹が相続できるのは亡くなった人に子供も親もいないときです。
(上記は更新日時点での内容となります。)
続きを読む >>
公正証書遺言作成までの手順
実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。
その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。
そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。
続きを読む >>
公正証書遺言の作成時の証人
公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。
親しい友人がいればその人にお願いすることも可能ですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため、守秘義務のある専門家に依頼するのが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士等の専門家をお薦めします。
なお、以下の人は証人にはなれません。
① 法定相続人
続きを読む >>
解決事例
-
- 2025.03.28
- 相続税申告が不要だと思っていたが、税務署からお尋ねが届いたケース
-
- 2025.01.28
- 相続税申告を2か月程度で終わらせられたケース
-
- 2025.01.09
- 相続手続き全般をご依頼いただいたケース